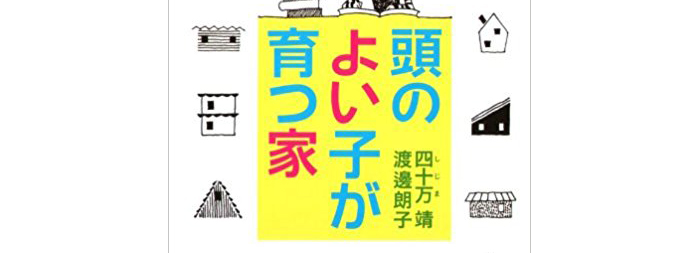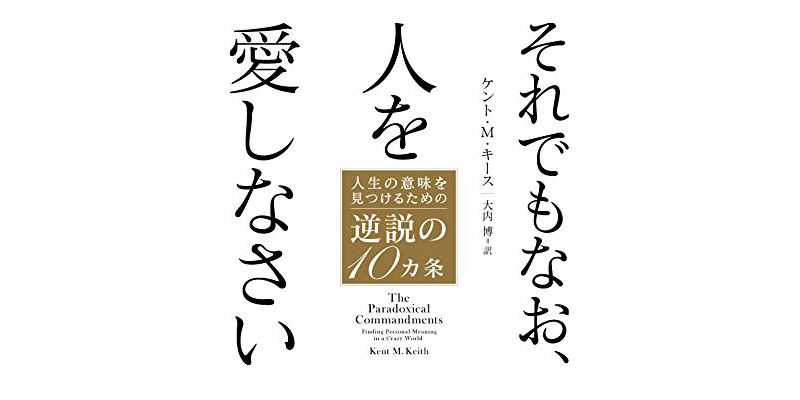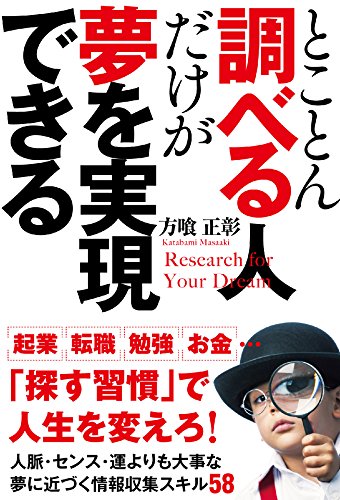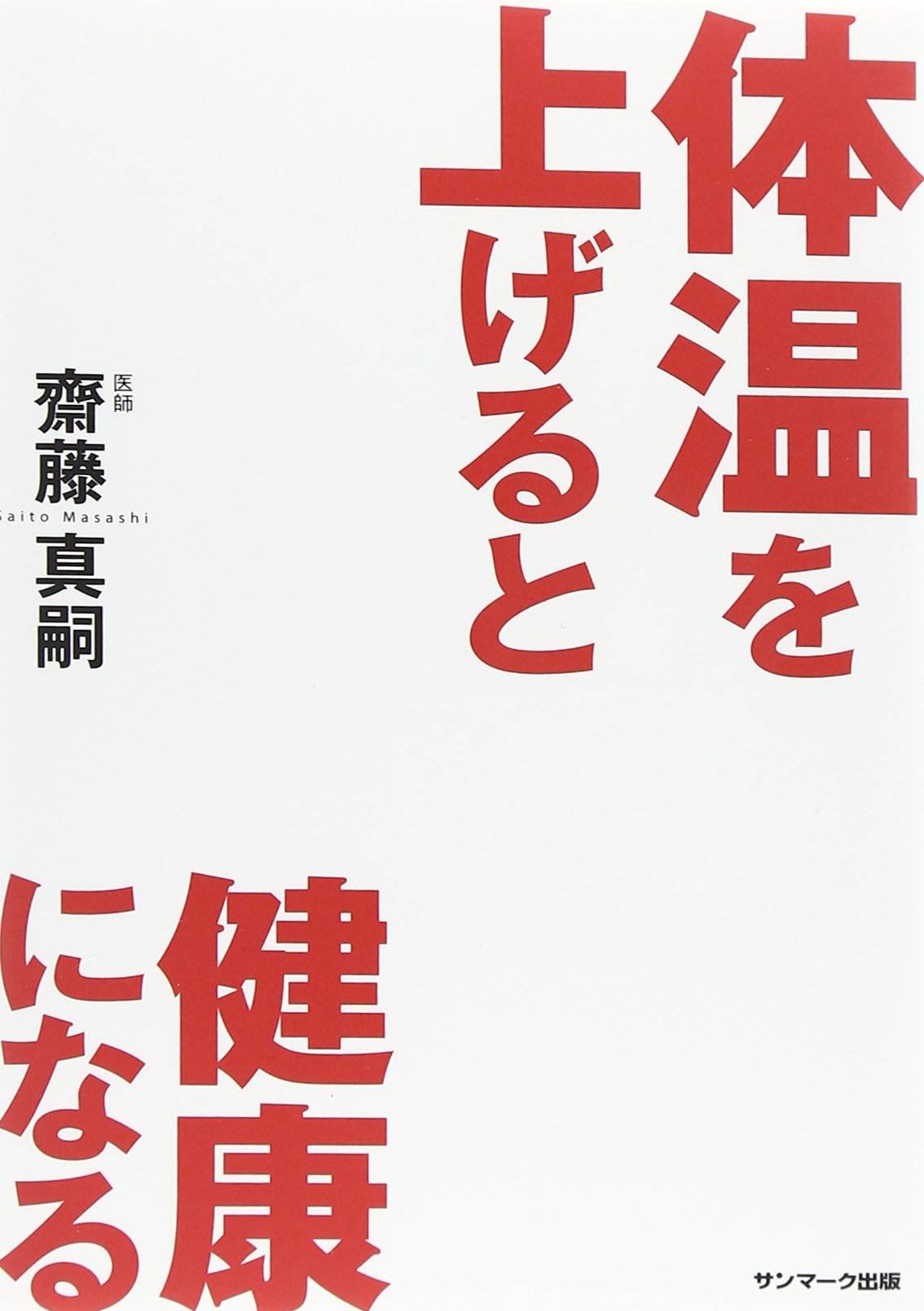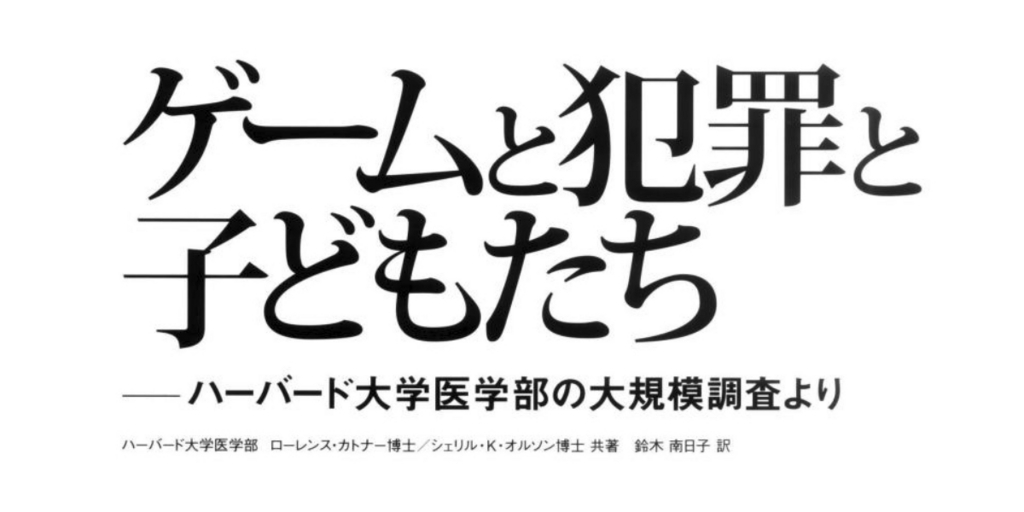目次
- はじめに
- 第一章 「頭のよい子」たちはこんな家で育ちました!
- 第二章 「頭のよい子が育つ家」とは、こんな家だ!
- 第三章 あなたの家をすぐに「頭のよい子が育つ家」に変える10ヶ条
- 第四章 建築学から考えた「頭のよい子が育つ家」の秘密
- おわりに
著者は
著者の四十万靖氏はスペース・オブ・ファイブという企業の代表だ。
【公式】頭のよい子が育つ家 |スペース・オブ・ファイブ株式会社|シリーズ五感の家として「住まい方」を提案する企業
親子のコミュニケーションをキーとした「住まい方」の提案である「頭のよい子」シリーズの第1弾、「頭のよい子が育つ家」のご紹介です。
スペース・オブ・ファイブという企業は、子供の教育学習環境を研究・調査しており、その結果から実際に住宅に活かせないか提案を行っている。
スペース・オブ・ファイブが親にとったアンケートがある。
Q1 「お子さんに子ども部屋を与えるとしたら、おうちの中のどんな場所がよいと思いますか?」
Q2 「お子さんにとって子ども部屋とは何をするところですか?」
回答は、
A1 「2階の南側陽あたりの良い場所」
A2 「子ども部屋=勉強部屋」
こういった回答が大半を占めたという。まあ、そうなるかなといったところ。
だが、スペース・オブ・ファイブが有名中学校に合格した家庭の学習環境を調査した結果
[box class=”blue_box” title=”調査結果”]
「宿題はリビングの卓球台でやる」
「子ども部屋がお茶の間になっている」
「自家製“移動式机”で家中どこででも勉強する」
「子ども部屋のドアはいつも開けっ放し」
「勉強道具を始めベッドまでもリビングに持ち込む」
[/box]
といった、アンケートとは間逆の結果が出たという。
「頭のよい子が育つ家」に変える10ヶ条
上記の結果から導き出されたのが以下の10ヶ条だ。
- 子ども部屋を孤立させないようにしよう
- 家中を勉強スペースにしよう
- おうちの中で、引越ししてみよう
- 子どもと家族の記憶に残る空間を演出しよう
- お母さんのスペースを贅沢にしよう
- 親父の背中を見せる工夫をしよう
- おもてなし空間を意識しよう
- 五感で感じられる空間にしよう
- 「書く」コミュニケーションを実現しよう
- ギャラリー空間を設けよう
要するに「頭のよい子が育つ家」とは、「子供が親兄弟とコミュニケーションが自然に取れる」だったり、「勉強場所を自由に選択できるノマド型」だったり、「子供の発想を阻害しない」家という事だ。
よく考えてみると僕自身も、本を読むときは「ベッドで寝転びながら読む」「ソファで読む」「机で読む」「トイレで読む」といった、その時の気分や体の調子をみて、読みやすいで場所を選んでいる。子供だけには1箇所でというのも酷だろう。
この本にも書かれているが、「頭のよい子」とはただ単に「勉強が出来る子」「暗記が出来る子」ではなく、「生き抜く力がある子」で、それが結果的に「学力が上げられる子」だと言う事。最近では、特に暗記だけが出来る子が多いように感じる。その為、想定外の事象が発生した場合、対応できなくなってしまう。「生き抜く力」を醸成するのは本当に重要だと思う。
著者は住宅を提案する側、住宅を売りたい側なので、多少のバイアスがかかっている事を考慮に入れる必要があるが、それでも人間の知的な成長の点で見ると納得できる部分は多い。